|
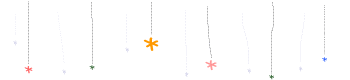 |
 |
- リボーン編
-
「ね。…ハヤト知らない?」
一方その頃。
会社では雲雀がハヤトの行方を探していた。
「ん? オレは知らないが?」
雲雀が聞いたのはリボーン。しかしそのリボーンも知らないと来る。
「困ったね…アップルパイを焼いたから食べてもらおうと思ったのに」
「お前キャラ変わりすぎだろ」
「うるさいよ」
と、リボーンはなにやら睨みつけてくるような視線を感じて。振り向くとそこには睨みつけてくる雲雀がいて。
「…なんだ」
「別に」
そういうが睨む視線は収まらない。むしろ口調にすら棘が含まれている。
「雲雀。言いたい事があるならはっきりと言え」
「これは僕がでしゃばっていい問題じゃないからね」
口ではそう言うがしかし納得はしていないというか。気持ちの整理がついていないといったところだろうか。
「…断るにしても。もうちょっと言い方ってモノがあったんじゃない?」
「なんの話だ?」
「ハヤト」
それでリボーンの中で合点が行く。ああなるほどと相槌を打つ。
「確かに僕には関係が無いかもしれないけど、でもさ…」
「関係なくは無いだろ」
雲雀の言葉を遮りながらリボーンが言う。雲雀は少し驚いたようにリボーンを見て。
「…ありがと。少し救われたよ」
「落ち込むハヤトが見たく無いって言うなら。お前が慰めてやればいいだろ」
そんなパイなんて作らずに。もっと別の方法でとリボーンは言ってくる。しかしそんなこと出来るわけがないと雲雀。
「あのね。僕が出来ることなんて高が知れてるでしょ。僕じゃ彼女は救えない」
「そうか? お前なら出来るだろう」
リボーンの言葉に雲雀は少しばかり違和感を覚える。何故だか彼は自分の事を異常に過剰評価してないか?
「…一応確認しておくけど。今ってハヤトの話だよね?」
「そうだな」
「ハヤトが落ち込んでて。それを浮上させるのが出来るのはって話になってるよね?」
「なってるな」
よしよし。ここまでは理解できる。分かった。問題はここからだ。
「じゃあ、更に一個確認なんだけど。…ハヤトが落ち込んだ原因は…」
「オレが現実を突きつけたからだ」
「…どんな風に?」
これを聞くのは雲雀としてはどちらかといえば遠慮したいのだがそれもままならない。我慢しよう。全てはハヤトのためだ。
「だから。お前が好きなのはオレじゃないだろうって」
「………ん?」
違和感。何かが違ってる気がする。何かが食い違っている気がする。なんだろう。ていうか。
…ハヤトが好きなのは彼じゃない? そうなのか?
雲雀は知っている。彼女の幼い、儚い、そして淡い心を。
その矛先はリボーンへと向けられていたであろう事を雲雀は理解していた。彼女はいつだってリボーンしか見ていなかったのだから。
…そんな彼女の想いが…違う?
「じゃあ…誰だって言うのさ。ハヤトが好きなのは」
雲雀の言葉に、リボーンは不思議そうにしながら。
「お前じゃないのか?」
なんて。真面目な顔で言ってきた。
……………。
時が、止まった。
いや、実際には止まってなんか無い。リボーンはいつも通りだ。ただ雲雀の時が止まっていた。硬直状態というのだろうか。
どれほど―――どれほどそうしていたのだのうか。
雲雀の口が…動いた。
「ど、どどど…」
「ど?」
ど…どう繋がるのだろうか。どうして。どういうこと。どれが…とリボーンがぼんやりと考えていると。
「どういう神経しているのさキミは―――――!!!」
どかーんと。雲雀が爆発した。
「なんだ違うのか」
「違うも何も、あの子は僕のことを男としては見てないよ!? あの子が僕に恋愛感情なんて有り得ないよ!!!」
「言ってて悲しくならないのか?」
しかし、とリボーンは思う。雲雀で無いのなら一体誰なのだろうかと。
「…骸、とか?」
「僕が許さないよ」
「お前のことは聞いてねえよ」
「…あいつも違う。あの子はあいつのことは兄とか、そんな目で見ているよ」
だから無下に離すことも出来ないんだよね…と雲雀はぎりっと歯を咬み締めた。しかし。ならば誰。
「ならツナか?」
「それも違う。あの子が沢田を見ている目は父親とか。そんな感じだよ」
「なら――――…」
………。リボーンは思いつかないのか、暫し硬直して…
「誰だ?」
降参した。候補が出てこなかったらしい。それを聞いて雲雀は頭を抱えたくなる。え。ていうか僕が言っちゃって良いの? と。
「だから………キミだよ」
「あ?」
リボーンは何言ってんだこいつ、みたいな口調で言葉を放ったあと。また考えて……
「なんでだ?」
…考えても分からなかったらしい。雲雀に答えを求めてくる。雲雀は溜め息を吐いてくる。
「何でもなにも…彼女が好きだって言ってるんだからそれだけで理由は充分でしょ! ああもう僕にこんなこと言わせないで!!」
「しかしな。あいつがオレが好きって。ありえないだろ」
リボーンは今までハヤトに厳しく当たってきた。それは仕事であり、そして最終的にはハヤト自身の為となり返ってきた。
しかしそれでも―――ハヤトには辛かっただろう。それが毎日も続いて。…面白いわけが無い。
そんなことをしていた自分に恋愛感情。…それこそありえないのでは無いだろうか。
その事を雲雀に告げると、雲雀は驚くことを反してきた。
「あのね…そんなに辛い日々をハヤトが弱音も吐かずに今までやってこれたわけって。キミは理解している?」
雲雀は大きく息を吸うと。
「キミのことが、好きだからに決まってるだろ!!!」
―――。
なるほど。
リボーンは素直に納得した。確かにそれは頷ける。
「キミがその想いをどう受け止めるかはキミの勝手だけど。でもそれを否定して。受け止めないことだけはやめてよね」
「…そう、だな」
「ハヤトに謝ってきなよ。感情を好きな人に否定されるのは、辛いから」
言って。雲雀は携帯をリボーンへ手渡す。それはGPS機能付きで。ハヤトへ渡されている携帯の位置が分かるようにとなっている。
「分かった。…あとな、雲雀」
「ん? 何?」
「あまり、ああいったことは大声で言わない方がいい。誤解する奴が出てくる」
「は…?」
そこで、雲雀は気づいた。
扉の影に誰かがいる。
「………まさか、雲雀さんにそんな趣味があっただなんて」
出てきたのは骸だった。
「…キミ。仮にもここはライバル会社でしょ。なんで来てるの」
「クフフ。ハヤトが休みだと聞いて何事かと思ってやってきたんですよ。しかし思わぬ情報を得てしまいました」
骸が含み笑いを零す。なにやら気味の悪い視線を向けられ雲雀は一歩身を引く。
「…? 何。なんでそんなに嬉しそうなの」
「だってライバルが独り減りました」
これは素晴らしきことですと骸はやっぱり笑みを零す。しかしはて。ライバル? 減った? 何が?
「…ちょっと待って。何。なんなの? なんの話?」
「クフフ。またまたそんなとぼけてしまって。今更隠してもなんの意味もありませんよ?」
クフフフフ。骸はいつもの3割り増しぐらいで笑っていた。何故だか雲雀は嫌な予感がした。
「いやー、あんなに熱烈な愛の告白。びっくりしてしまいましたよ」
「は?」
愛? 告白? 何のことだろう。雲雀は考える…が分からない。
その横でリボーンはやれやれと溜め息を付いていた。彼には原因が分かっているらしい。
「でもまさか、貴方が男色家だとは知りませんでしたよ」
てっきりハヤトが好きだと思い込んでいたんですけど、と言う骸に雲雀は絶句していた。
「…だから待って。男色家って…この僕が?」
ありえないと呟く雲雀。自分にその気はないと。
「もー、そんな言い訳なんて通用しないんですよ? さっきあんなに大声で言ってたじゃないですか」
大声で。言ってた。雲雀は少しだけ過去を回想する。
キミのことが、好きだからに決まってるだろ!!!
あれか―――――!!!
しまった。確かにあれだけだと誰が誰に対して言っているのか不鮮明だ。しまった。不覚だ。
「ち、ちが…あれはっリボーンも何か言って!!」
「雲雀…悪いが、お前の気持ちには応えられない」
「何泥沼化させてるのー!!」
あああああもー、どうすればいいのか。ていうかリボーンは何面白いからって事態を悪化させているのか!
「あーあ、ふられちゃいましたね」
「うるさいよ!!」
「悪いな雲雀。オレの好きな奴は―――…」
と、不自然な所で言葉を区切るリボーン。見ると彼は何かに気付いたかのような顔をしていて。けれどどこかぼんやりしたような顔をしていて。
「…? どうしたのさ」
「いや――――…な。今オレの好きな奴はいないって言おうと思ったんだが、そしたらハヤトの顔が出てきた」
「は?」
「なんでだ?」
疑問。そこにあるのはただそれだけ。
雲雀は思わず頭を抱える。それしか出来ない。ていうかもう、どうしよう。
「え…これって言うの? 言うべきなの? 言って良いの? ねぇ」
「クフフ…これはとんだ大穴でしたね。…ただ単に興味が無いのかと思ったらただ気付いていないだけとは…」
「なんの話だ?」
…ああ、これが天下のリボーンなのだろうか。やることなすこと天下一品。行動は全てパーフェクト。無駄が無く隙も無い。まさに超人。まさに天才。そのリボーン・が。
「…え。なにコレ僕が言うの? 何今回の僕の役回り。不憫過ぎない?」
「クフフ。確かにそうかもしれないですが口で言うのはどうかと思いますよ?」
溜め息。雲雀は溜め息を付く。それは重くて深い溜め息。そして顔を上げて雲雀はリボーンを睨む。恨みとか辛みとか色んなものが詰まった睨みだった。
「良かったね。両想いだよおめでとう」
「あ?」
「いいからさっさとハヤトの元へ行けば? そうして謝って。あと抱きしめてあげるといい」
雲雀はそれだけ言うと早く行けといわんばかりにリボーンを部屋から追い出した。リボーンの抗議も聞き入れない。
「おい、一体なんの話だ。あと両想いって何のことだ」
「だからうるさいって。…ああもうなんだかハヤトが可哀相になってきた。あの子が一番不憫で報われないよ! なんで、こんな奴・・・!」
取り付く島も無い。やれやれ、まぁまずはハヤトのところへ行くことにしよう。リボーンは走り出した。
―――そういえば…今日はハヤトもだが、一度もツナの顔を見ていないなと思いながら。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ハヤト編)→ |
|
|
|