|
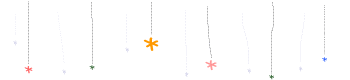 |
 |
- ハヤト編
-
ハヤトは走っていた。
その速度は決して速くは無いが、それでも何かを一生懸命振り切るように。
そんなハヤトを追いかけるものは―――無い。
なのにハヤトは走っていた。必死に。懸命に。
まるで、なにかから逃げるようにと。
夕方の公園で影が一つとなって。ハヤトの目は見開かれていた。
触れるだけのキス。しかしそれはハヤトにとって充分に刺激的で。…触れられている部分が、熱い。
やがて、社長の舌がハヤトの唇をちろりと舐めて…ハヤトは正気を取り戻した。
「ん………っゃ、」
思いっきり社長を押し出して。何とか社長の身体から追い出る。知らずハヤトの瞳から涙が零れていた。
社長と距離を取ったあと、ハヤトは思わずかぶりを振って走り出した。そのまま振り向かず消え去って…社長はそのさまをずっと見ていた。
「…ふふふ。ほら、キミがいつまで経っても手を出さないからオレがつば付けちゃったじゃない?」
社長はくすりと黒く笑いながら…ずっとハヤトが走っていった方向を見ていた。
「キミがどう動こうとも勝手だけど…オレだって。彼女を譲る気は無いんだからね…? リボーン」
社長がそんなことを言っている間もハヤトは走り続ける。早くも息が上がっているが、それでも足は止まらない。
―――ハヤトは、自分が情けなかった。
いきなりキスされるだなんて、悲しくて…悔しくて。
自分には、そう。………想い人がいるのに。
沢田社長から離れたとき、そして涙が頬を伝っていると言うことに気付いたとき。彼女の心に浮かんでいたのは…リボーンだった。
「リボーン…さんっ」
彼にはこの想いは違うと。勘違いだと言われたけれど…そんなはずは無い。
こんなにも切ない想いが恋心でなくて一体なんだというのか。確かに自分はこれが初恋だけれどでもそれでも。
「リボーンさん、リボーンさん、―――リボーン、さん・・・っ」
逢いたかった。あの人に。
いつも無表情で、厳しくて。でも…頑張った日には頭を撫でてくれて。
あの人がいると、ふわっと世界が変わる。
心がステップを踏んでる感じ。胸の奥がじんわりと暖かく。ほんわかに。
この事を姉に相談して。そうしたらそれは恋だよって。
それは考えても見なかったこと。それは思いも付かなかったこと。だけど気付けたこと。
気付いてからは彼と会うのがなんだか恥ずかしくって。いつも以上にミスの連発。
…あの日の晩だって。そう。
恋だと聞いてから胸のどきどきが治まらなくて。眠れなくて。
そうして、そうだと思い立った。
そうだ、お菓子を作ろう。
この間お姉ちゃんが作っていたクッキー。あれを作って、リボーンさんに食べてもらおう。
レシピはお姉ちゃんに書いてもらって。材料は雲雀さんに頼んで。
急に贈っても驚かないかな。でも大丈夫だよね。いつもお世話になってるお礼って言えばきっと。
…でも。そうしてお菓子を作っているうちにリボーンさんが、きて。触れられて、距離が近づいて…
気付いた時には、感情は爆発していた。
そして…そして。
ハヤトの脳裏に昨日の晩から先ほどのことまでが高速で再生される。そしてまた涙。
「ぅ、ぐ、………リボーン、さん・・・!」
涙で周りが見えなくなったのか、どんと誰かにぶつかって。ようやくハヤトは足を止めた。
「あ、ご、ごめんなさ…っ」
「別に構わん」
上から降ってきたのは、聞き覚えのある声。はっとハヤトは目を見開く。
「え………」
見上げるとそこには…そう、ずっと名前を呼んでいた。ずっと逢いたいと思っていたリボーンその人。
「ぇ、あ、ああ、………やぁ!」
ずっと逢いたいと。その顔を見たいと思っていたはずなのに、いざ目の当たりにするとハヤトは急に怖くなって。逃げ出したくなって。
「ハヤト…? おい、どこに行く?」
「や、や、やあぁぁ…だめ、駄目なんです、今は駄目なんです!!」
なんだか自分は汚れているような気がして。今彼に触れられたらその彼すら汚れてしまいそうで。それがハヤトは怖くて。
いやいやと首を振って。涙を零して。ハヤトは逃げ出そうとするも腕を掴まれていて。
「リ、リボーンさ…は、なして、くださ……」
その手を、どうにかハヤトが引き剥がそうとした、との時。
地面が揺れた。
「え? …あ、ぁ?」
ぶわっと。ハヤトの全身から冷や汗が流れる。鼓動が一気に早くなって。身体ががくがくと震えて。
「え、や、あ、ゃ、だ…」
それは恐怖。幼き頃の精神障害。揺れる地面、崩れ落ちる道具、狭く閉じ込められて…手が、痛くて…
「や、やぁ、いや、ぁぅ、やああああああああ!!!」
過去のトラウマに直面しきれなくなったハヤトは思わず…そう思わず。直ぐ傍にいたりボーンに抱きついて。
「ハヤト…? おい、ハヤト。大丈夫だ。落ち着け」
「や、ぁ、あぅ、やです…、助けて、助けてリボーンさん!!」
錯乱したように取り乱し。暴れるハヤト。なだめようとするリボーンを引っかいてしまうほど。
ハヤトは目から大粒の涙を零しながら。じたばたと暴れていた。怖い怖いと泣き叫んでいた。
「ハヤト!!」
リボーンはハヤトをぎゅっと抱き締めた。力一杯、ぎゅっと。
ハヤトの目に正気が宿って。先程の涙とはまた違う意味の雫が、零れる。
「リボーン、さん…」
ハヤトはそっと。ぎゅっと。リボーンに抱きつく。スーツの向こうの温もりがあたたかくて。それに安心する。
ああ、私はずっと。これが欲しかったんだなって。そう思いながら。ハヤトは目を瞑った。
「落ち着いたか?」
「は、ぁ、はい…」
地震が静まって、それから暫く経って。ハヤトの震えが治まったころ。リボーンは静かに聴いてきた。
「も、だい、じょうぶです…あはは、みっともない所見せちゃって…その……」
ハヤトは自分から離れようとするが、声は涙声で。それは無理をしていることがばればれで。
「無理しなくていい」
言って。リボーンはハヤトを引き寄せて…ぎゅっと。また抱き締めて。
「ぃえ、あの、ホント、だ、大丈夫なんです。リボーンさんにお手数をお掛けするには…」
「いいから」
「は、はぅ」
なんだか、何かが違う気がする。いつもと何かが。…雰囲気? いつもよりもなんだか柔らかい気がして。…でも、何故?
「苦手なのか?」
上空からリボーンが問い掛けてくる。ハヤトはちょっと赤くなりながら。
「は、はい…あは、は…ずっと昔――…5年? いえ、もう7年ですね…それぐらい昔に、初めて地震を体験して」
ぽつりぽつりと体験を話すハヤト。そしてそれにリボーンは何か引っかかるものを感じる。はて。なんだろうこれは。
7年前。………ああ、確かに地震があった。それは少し大きなもので。その地震があったとき、自分は…そう、確か…
と、ハヤトの視界にリボーンの手が写る。左手の手の甲。…赤い線が走っていた。
はっと、ハヤトは思い出す。さっきの地震で自分は取り乱して、何かを引っかいたのではなかったっけ…?
「あわ、あわわわわわわわ。すみませんです、ごめんなさいリボーンさん!」
「ん? …ああ、別に構わん。気にするな」
しかしそういわれても無理というもの。ハヤトはポケットからハンカチを取り出して。リボーンの手に巻きつけて。
…そのハンカチに、リボーンは見覚えがあった。けれどそれは、遠い昔に無くしたはずで。
「ハヤト。―――これは?」
「え? あ…あは、これは…お守りなんです」
「お守り?」
「はい。…ハヤト、地震にあったとき落ちてきた道具に閉じ込められちゃって…そのとき出たくて。どんどんって道具を叩いたんです」
でも出れなくて。怖くて。また叩いて。そうしていたら皮が破けて。痛くて。怖くて。
「それから暫くして、誰かがハヤトを助けてくれたんです。…このハンカチは、その人が巻いてくれたんです」
ハヤトの夢はいつかその人にあって。そしてこのハンカチを返すことなんですよとハヤトは微笑みながら言った。
けれどリボーンの頭にはそんなハヤトの言葉もろくに入ってきてなくて。ぱちぱちとピースがはまっていくような感覚を味わっていた。
7年前。少し大きな地震。小学校低学年の女の子。道具置き場の倉庫。怪我をした手。泣きじゃくる声。―――そして無くしたはずの、ハンカチ。
「―――お前か」
「はい?」
…まぁ、そんなこんなで。
獄寺ハヤトの幼き頃からの願いは本人が気付かぬまま叶ってしまった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(エピローグへ)→
|
|
|
|