|
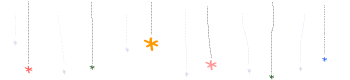 |
 |
僕の名前は『六道 骸』。
かつてはボンゴレに敵対していたもの。輪廻をわたるもの。禁弾の使い手。そしてボンゴレ十代目の霧の守護者。あなた方のお好きなようにお呼びください。僕には今、自分でふさわしい名前と思っている名前があるのですから。それは楽園の番人。世界で一番脆く儚く美しい彼女のための楽園を作り出す者。僕はこの仕事に今までに無い生きがいを感じているのです。
楽園は殺風景な丘の上にありました。真っ白な塀に囲まれた真っ白な建物。最初、そこで彼女に与えられた狭い過ぎず広くも無い部屋の中にはベッドと小さなテーブルと対になる椅子だけがありました。
けれど着たばかりの頃、白すぎる壁を彼女が怖がるので僕は彼女の好む落ち着いた色で床と壁を染め上げました。いつも清潔にしてある真っ白なシーツのかかったベッドを彼女は不安がったので僕は使い古した素朴なベッドと部屋にあった色のシーツに取り替えてあげました。小さすぎるテーブルと椅子は馴染めないと彼女が嘆くので僕は彼女がかつて使っていたものと似たテーブルを探し出し椅子と一緒に与えてあげました。そして最後に青すぎる空は目に痛いと彼女が嫌がるので僕は窓から見える景色をずっと曇りか雨の中の光景にし続けました。
彼女の望むものだけで囲まれた彼女のためだけの世界。けどそれでも彼女の心は満たされませんでした。楽園には彼女が一番望むものが無かったからです。
一人は淋しいと呟くから僕は彼女と中の良かった友達に会わせてあげました。
一人は辛いと叫ぶから僕は彼女の一番美しい思い出の中にあった両親と姉を呼び出しました。
一人にしないでと彼女が泣いたから僕は彼女の家族の代わりに人形をたくさん贈りました。
けれど全ては僕の作り出した幻覚です。夢から覚めれば彼女は白い壁の部屋で白いシーツにくるまれて人形を抱きしめたまま一人で目を覚ましては涙を流して暴れだすのです。それでも一時でも彼女が微笑んでくれるなら、喜んでくれるならかまわない。そう思ったから僕は彼女のために夢を見させ続けました。それは僕の我侭のせいでもあったんです。
僕は本当に彼女が望む人間を作り出しませんでした。
彼女が一番求めて会いたくて愛している人間の幻覚だけは僕は作らなかった。それは僕の醜い欲望と渇望と嫉妬せい。・・・そしていつかは全てを受け入れてくれるかもしれないという淡い期待からです。
でも彼女は現実を受け入れず、いつまでも僕が作り出した幻覚の世界で止まない雨を見続けていました。現実の青空は彼女には重たすぎたんです。
けど、あの日。僕の作り出した楽園にやってきた少年によって彼女の世界は変わりました。
今まで抱きしめ続けた人形はゴミ箱へ捨てられ、真っ白な壁に怯えることも無くなり、僕の作り出した夢を見る時間は減りました。『彼』がきてから。彼女が一番求めて、そして彼女の楽園に唯一足りなかったもの。ずっとずっと待ち望んだ『彼』が彼女の元に帰ってきた時、彼女の楽園は姿を変えたのです。
でもそれは世界が再生のしていく姿ではなく僕には本格的に崩壊していく姿に見えました。
「そうは思いませんか?ボンゴレ」
薄ら笑いを浮かべて彼を見下ろしている僕。彼女のいる建物を取り囲む壁に背を当てガクガクと震える彼は寄りかかるものがなければ今にも倒れてしまいそうなほどに怯えていました。当たり前ですよね。今まで普通の学生として生活してきた彼がマフィアの・・・それもボンゴレの幹部の一人である僕に追い詰められているんですから。
けど、僕は彼を殺すつもりもありません。むしろ生きていてもらわなければ困るのです。僕のためにも彼女のためにも。
「あなたには此処にいてもらわないと」
「ぼ・・・ぼくは・・・・いやだ。あ・・・そこにはいきたくない」
「何をいってるんですか。貴方だって会いたがっていたでしょう」
「そうだけど・・・こんな形じゃ・・・」
「それにここに入ってきたのは君だ」
僕達は強制して彼を此処に連れてきたわけではない。彼がやってきたのはほんの偶然。この楽園は永遠に僕達だけの存在だけで終わるはずだったのに、そこに入ってきたのは彼の意思です。
「・・・綱吉さーん、どこにいるんですかー?」
遠くで声が聞こえる。この世界でも最も美しい彼女の声。
「ほら・・・ハヤトが呼んでます。帰りましょう?」
彼の震える唇が否定の言葉をつむごうとしていましたが僕はそれを無視して彼の腕を引きました。無理やり引きずる形でしたが力で適うはずも無く、彼は最後の抵抗と言わんがばかりにぶつぶつと何かを言いながら僕の後に続きます。
しばらく歩くと彼女の呼ぶ声がぴたりと止まりました。そして代わりに聞こえてきたのは泣き声。
「うぁ・・・ああぁ・・・ひっく・・・・やぁ・・・・」
嗚咽と共に聞こえてくるのは何かを壊す音。コップかお皿でしょうか。時折声に混ざって陶器の割れる音も耳についてきました。僕の後ろではその音を聞きながら彼が震えています。でもそれも僕は無視して彼女のいる部屋へ急ぎました。
「早く行ってあげないとかわいそうですね」
音の一番大きな部屋の前に行くと僕は扉を開けます。
中は・・・悲惨なものでした。引き裂かれたシーツに壊されたテーブル。割れたカップに散らばったお菓子とお茶の残骸。そして部屋の中心には荒い呼吸を繰り返す美しい人。
「ハヤト・・・帰ってきましたよ」
彼女を落ち着かせようと声をかけましたが彼女の口からは意味を成さない言葉が繰り返されるばかりでコチラを振り向こうともしません。けれど一瞬だけ、彼女が頭をこちらに向けたとき・・・彼女の表情は一転しました。
「綱吉さん!おかえりなさい」
にっこり微笑んで駆け寄ると僕の後ろに立つ彼に飛びつきます。
「今日のお仕事は終わったんですか?」
「・・・う・・・うん・・・」
微笑む彼女に擦り寄られて彼はたどたどしく答えます。そして二、三言交わすとそこで始めて僕に気付いたらしく、彼女は照れたように彼から体を離しました。
「なんだ骸来てたのか!もう・・・来てたなら言ってくれればよかったのに」
「すみませんね。あまりにも二人が仲睦まじいいので声をかけそびれてしまいましたよ」
僕がそういうと彼女は照れたように微笑みます。僕もその笑顔を見て微笑みます。後ろで立っている彼は複雑そうな顔でしたが彼女が顔を向けると戸惑いながらも笑顔を作ってくれました。
「それじゃあ僕は失礼しますね。あとはお二人の時間を楽しんでください」
幸せそうな彼女の顔を見て僕は早々に部屋を後にします。この後のことは容易に想像がつきますのでしばらくはこの場を離れたほうがいいでしょう。幸せそうな彼女と彼女に愛されている彼。
その二人さえいればここは完成された楽園なのです。
それは何処までも脆く、儚く、
しかしだからこそ美しく見える病みの色。
|
|
|
|