|
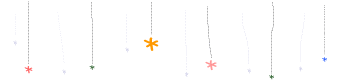 |
 |
あの時に手を重ね合わせたのはこれで最後になりそうだったからかもしれない。
「なに・・・やってるんだ?」
くすぐったそうに隣に寝転びながらくすくすと笑う彼女。
僕はそんな彼女を愛しく思いながら指も絡ませて握り締めあう。ぎゅっと、両手を重ね合わせて。何の意味も無い行為だけど、僕にはこれが大事な儀式のような気がしてならなかった。
「なんだ、寂しいのか?」
「寂しい?まさか・・・」
そう言いながら向かい合わせになった顔をゆっくりと近づけてキスを落とす。
寂しくないなんて嘘だ。明日から僕達は別の国へと旅立つ。君はファミリーの中心であるイタリアへ。僕は祖国の日本へ。直ぐに会える距離じゃない。仕事の内容だって早めに終わったとしても片付けだけ一週間はかかるような大仕事だ。お互いそれぞれの地での敵マフィアの殲滅。命がけの仕事。
「帰ってきてよ・・・」
「帰ってこいよ・・・」
渡り鳥が生まれた町に帰ってくるように、お前も自分のところに帰ってきて。それはささやかで絶対の約束。
「愛してるよ」
何度も繰り返した言葉を呟くと、僕はいつものように指で君の掌を叩いた。僕達のいつもの合言葉。秘密の暗号。
けどコレがあれば何時でも僕達は愛し合える。
彼女は嬉しそうにそれを答えると、同じリズムで僕の掌を叩いた。
愛してる。
口に出さなくても伝わる言葉。僕が彼女と付き合い始めたときに二人で決めた二人だけのリズムだ。
いつか口が利けなくなっても、字がかけなくなっても、耳が聞こえなくても君に愛の言葉が伝わりますように。そんな願いを込めあって決めた最高の愛の言葉。
僕はその時の事を思い出して笑みを作る。彼女もそれに気づいて微笑む、なんて穏やかで幸せな時間。明日には戦場へと旅立つ僕達だけど、この時間だけは誰にも汚されたくなかった。
「帰ってくるよ」
「帰ってくるから」
もう一度繰り返してキスをして。そして最後の夜に君の肌を味わった。
最後だから、コレで最後だから。
この仕事が終われば君はマフィアを抜けて穏やかな日々が約束される。そして僕が用意した小さいけれどのんびりした雰囲気の漂う田舎の家に一緒に住もう。
その約束の証は僕と君の左手の薬指で輝いている。
最後だから、コレが最後の別れの夜だから・・・。
翌朝目を覚ますと、僕の横のシーツは冷たくなっていた。
ベッドサイドにおかれた君の朝の挨拶代わりのメモに目を通して、僕も仕事へ向かう用意をする。
いつもどおり仕事を終わらせて、いつもどおり君のところに帰ってこよう。大丈夫、僕は強いから。君の強さも知ってるから。
「いってきます」
そして数日後に僕の口から出た、
「おかえり」
この言葉を口に出したとき、僕の目の前に君の姿は無かった。
代わりにあるのは小さな箱。
黒く焼け焦げた指が数本。
銀色の綺麗な頭髪の束。
約束の証がはめられた左手。
それが君の代わり。
帰ってこなかった君の代わり。
帰って来れなかった君の代わり。
「嘘つきだね・・・君は・・・」
あの時に手を重ね合わせたのはこれで最後になりそうだったからかもしれない。
僕は先の無い左手に自分の指を絡ませる。
冷たい掌は気持ち悪い。胃がむかむかする。
けれど愛しいと思う気持ちは止められない。
僕はいつものように指を叩いてリズムを取る。
けど、そんな事をしてもくすぐったそうに笑う君はいなかった。
嬉しそうに微笑む君を見ることはもう無かった。
猫は王様が好き。
王様は猫を愛している。
王様は猫を別荘に連れて行く。
自分のツガイにするために。
王様の城で腹ペコの犬が鳴く。
王様は煩い犬を黙らせたい。
王様は犬に猫の体を食べさせる。
犬の空腹は満たされた?
食べるのを拒む犬。
喜んで食べる犬。
餌の材料を知りたがる犬。
ならば自分はそれだろう。
王様は別荘に帰る。
猫は小鳥を生んでいた。
(続きます) |
|
|
|