|
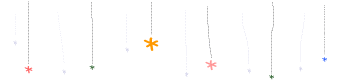 |
 |
ここは並盛。知らぬうちにオタクの聖地と化してしまった街。
しかしそんなことに気づかない一般市民は何も知らず平穏な毎日をおくっています。このシリーズの主人公の一人である獄寺隼人もその一人。彼は恋人がオタクだったりその友達や懐いてくる相手がやっぱりオタクだったり、恋人のためにコスプレしたりナニしたりしてましたが根っこは立派な一般人です。最近になってFAミコンのオーバーオールの叔父様を操るアクションゲームなんぞに手を出しましたがギャルゲーなどは存在すら知りません。というか最近まで「萌え」と「燃え」の違いすら良く分かっていませんでした。そもそも未だに理解できていない部分が多すぎです。
まぁそんな彼と恋人達が住む並盛ですが、彼はまだ何も知りませんでした。この街が抱える大きな秘密。そしてアキバでも無いのにオタクの聖地と銘打たれている理由を。
その日も買い物袋を片手に下げた獄寺はとある古びたアパートの前で熱い視線を送っていました。彼の視線の先にあるもの。それは微妙な顔をした巨大オブジェです。
「し・・・渋い」
思わず零れたつぶやきに彼は加えていたタバコをポトリと落としてしまいましたが、そんなことも関係ないといわんがばかりに彼の心のこの巨大オブジェに夢中でした。
困ってるんだか笑ってるんだか読み取れない素敵な表情。何処からが首で体なのか分からないボディバランス。原色バリバリで疲れ目に染みそうな配色。全てが完璧な黄金比。しかしその芸術は獄寺をはじめとする一部の人にしか受け入れられないものでした。例えば彼の後ろを歩く親子。子供はオブジェの顔に泣き出し手を引く母親は『見ちゃいけません』と早足でその場を去っていきます。けれどオブジェに気を取られている獄寺にはそんなこと関係ありません。後ろで某賭博漫画のごとくザワザワと声が聞こえてこようが陰口を叩かれようが彼のハートはオブジェに打ち抜かれていたのです。
「渋い・・・渋すぎる・・・」
ほうっとため息をこぼす獄寺。するとどうでしょう。彼の背後でザワザワしていた民衆の中から一人の男が現れ彼の方に手を伸ばしました。
「・・・おい」
低い声と肩におかれた手に思わず顔を向ける獄寺。オブジェに向けていた熱い視線を一変させ、自分に声をかけてきた強面の男に思わず低くうなります。
「なんだテメーは・・・」
「・・・・・・ザンザス」
「は?」
「ザンザスだ」
2回言われて獄寺はやっと彼が自らの名前を名乗っていることに気がつきました。
「で、そのザンザスは俺に何のようなんだ」
「・・・・・・中に入れ。茶を出してやる」
「は???」
さっき以上に謎の言葉。獄寺の眉間の皺は見る見るうちに深くなっていきますがザンザスはそんなことはお構い無しな様子で話を進めます。
「こんな所に突っ立ってんなカスが。通行の邪魔だ」
「邪魔って言われる筋合い、お前には・・・・」
「そんなに気に入ったんなら中でゆっくり見せてやる。これ以上の物もな・・・」
そういってニヤリと笑うザンザス。その顔に後ろでざわついていた民衆は悪寒を覚えました。凶悪すぎます。怖すぎます。先ほど泣き喚いていた子供など恐怖で逆に声も出なくなってしまっていました。それくらい・・・ザンザスの笑顔は恐ろしかったのです。
でも獄寺はザンザスの顔よりももっと別の言葉に気をとられていました。それは先ほどのザンザスの言葉。
「ゆっくり見せてやるって・・・まさかこれ、お前のなのか!」
「あぁ・・・というかお前がさっきから入り口をふさいでいるアパートごと俺のもんだ」
「マジで!」
キラキラと両手を組んでザンザスを見上げる獄寺。表情はまるで幼子のように無邪気でした。
「わぁーすげえええ!!」
「わかったならさっさと来い」
「サンキュー!あ、俺は獄寺隼人って言うんだ」
「そうか」
簡単に自己紹介を済ませると意気揚々と中に入っていく獄寺。そしてアパートの管理人と共に中に入ったのを見送ると通行人達はやっと普段どおりの日常を送り始めます。
雲雀達の住むマンションの日陰となるところにある築20年以上を誇るアパート。風呂無し、トイレ共同。一見すると時代に置いていかれた様な古き良き佇まいの前で獄寺のハートを鷲づかみにした謎オブジェはどーんとその日常を見守っているのでした。
「でさー。すげえんだよ!ちょっと見せてもらっただけなんだけど絶妙な顔をしたマトリョーシカのセットとか造形が崩れたトーテンポールとかあってさー」
「へー・・・」
「見るからにパチモン臭いネズミーランドのキャラの縫いぐるみとか・・・って雲雀。話し聞いてるのか?」
「うんうん・・・そう」
活き活きと今日あったことを話す獄寺。その傍らで持っていた薄い本を広げ夢中になっている雲雀。どう聞いても生返事にしか聞こえないことに怒った獄寺は雲雀が持っていた本を上からするりと取り上げました。
「せっかく二人っきりなんだから俺の話を聞けー!!」
「ああああ!!せっかく良いところのなのに!!!返してよハヤリン」
「うるせー!いつも雲雀の話聞いてやってるんだからたまには俺の話を聞いてくれたって良いだろう!!それにお前さっきからナニをそんなに夢中になって読んで・・・」
腹が立った獄寺はパラパラと取り上げた本のページをめくります。
1ページ。2ページ。めくられていく度にどんどんと表情をこわばらせていく獄寺。そして最終ページを閉じたとき、呆れたように獄寺は恋人の手に本を返しました。
「なんだ・・・これ・・・」
「ヴァリアーって僕の好きなハヤリーナのサークルの最新刊だよ」
「ハヤリーナ・・・にしては俺の知ってるハヤリーナと絵が随分違うみたいだけど・・・」
「だろうね。これは同人誌だから書いた人の絵が色濃く出るし、何よりこのサークルの書き手の絵は独特だからね」
そう良いながら再び最初から読み始める雲雀。自分の話を聞いてもらうことをあきらめた獄寺はその背後から抱きつくと首越しに中身を眺めます。
よく言えば元祖少女マンガ。悪く言えば古の画風。あぁ、そういえば前に姉貴が読んでいた『ガラ●の仮面』とか『ベル●イ●の薔薇』とか『ア●ックNo.1』とかこんな感じだった気がする。背中にバラを背負ってもおかしくない画風に獄寺の意識はぼんやりと関係ないところに飛んでいました。
同人誌は雲雀が書いたり骸達が自分の書いたりしたものを持ってくるため見たこと無いわけではありません。でも獄寺が知る同人誌に書かれた絵柄はいまどきの若者の好みそうなポップで可愛らしいものが多かった気がします。
「この人は僕たちが幼いうちから現役の人だからね。その頃から絵柄も変わってないからハヤリンが古臭く感じてもしょうがないよ。でも僕はこの絵だからこそ良いと思ってるんだ。繊細な線と耽美と言われるストーリー。ベタな展開と激しすぎる心理描写。・・・何を隠そう、僕がはじめて買った同人誌がこの人のものだからね」
読み終わった本を胸に抱きしめそう呟く雲雀。その声にやっと獄寺は意識を取り戻しました。
「初めて買った・・・」
「うん。最初は僕も絵柄が合わないと思ったんだけどね。けど読み始めたら止まらないし内容は濃いし・・・気がついたら虜になってて大ファンになってたよ。ファンレターも何回も出してるし向こうの人にも最近は名前を覚えてもらえたんだ。新刊が出るたびに感想を送ってるしね」
「本当に好きなんだな」
「うん、でも」
雲雀はそこで表情を曇らせました。
「一度も本人に会ったことが無いのは残念かな。どんな人がこの漫画を書くのか一度見てみたいんだけど本人は売り子に任せて会場には来ないし。・・・まぁでも会わないほうが良いこともあるかもね」
「そうっか?俺なら会ってみたいと思うけど」
「実際に会ってみて自分のイメージが崩れるのが怖いってのもあるかもしれないけど・・・なんだろうな。憧れは憧れのままが良いって言うか、手が届かないままのほうが良いというか・・・・。奥付の住所を見ると同じ並盛の人らしいんだけどね。でもやっぱり会ってみたいとは思わない」
「・・・雲雀」
そう宣言する雲雀の真剣な表情に胸をときめかせる獄寺。恋人の言うことも分かります。憧れは憧れのままで美しく残しておきたい。雲雀の中でその本の作者は不可侵領域なのでしょう。
それは何処と無く美しくも切ないもの。そう感じながらも獄寺は何も言えずに同意の意味を込めて頷くのでした。
その頃、お隣のアパートでは・・・修羅場を迎えていました。
「ボス。ここのベタは終わったぞ」
「トーン貼りかんりょ〜」
唇にピアスをつけた男と派手な装いの男がそう叫ぶと部屋の上座に座る男に持っていた原稿を渡しました。
「ペン入れはコレで良いかい」
小さな子供もそう言って仕上げた原稿を手渡します。
するとその声を聞いてボスと呼ばれた男・・・ザンザスはゆっくりと下書きを入れている机から頭を上げました。
「・・・・・フン」
一瞥してそれだけザンザスはそれだけ言うと再び途中の原稿に視線を落とします。するとその場でにいた男達の緊張が一瞬にして和らぎました。
「良かった。ボスに気に入っていただけたみたいだな」
「はぁ〜・・・今回もコレだけのページ数仕上げるの大変だったんだから」
「いつもよりアシスタント代多くもらわないと割が合わないね」
胸をなでおろすとピアスを嵌めた男レビィはふと部屋の中を見渡し空席となっているアシスタント用の机を睨みつけます。
「まったくスクアーロもベルもこの忙しい時期に何をやってるんだ」
「ふふふ・・・多分、ボスには言えないお仕事をしてるんじゃないかしら」
意味深に笑うのは自らの服についたトーンを払い落とすルッスーリア。彼は椅子に座っている子供・・・マーモンに小さく耳打ちをします。
「相変わらずなのあの二人」
「あぁ。たまに僕にアシスタントを頼んでくるよ。でも売り上げは悪くないみたいだよ。良くも悪くもあの二人の出す本は話題性があるみたいだからね」
「まぁ、私も一度読ませてもらったけどね。でも・・・あれじゃあボスにはいえないわよね」
そう言ってここにいない二人を思うルッスーリア。このヴァリアーというサークル以外でも活躍する二人の出した本は俗にいうトラウマ本でした。
その真逆に位置するのがザンザスの出す乙女本。
キラキラした描写と昔ながらの絵柄。ベタな展開と純愛とラブロマンス。消して濡れ場を許さないザンザスの漫画は老舗の味のように固定ファンの多いものでした。
「とてもじゃないけどあの顔からあの繊細な話と絵が生まれるとは未だに信じられないわ」
ポツリと一人原稿に取り掛かるザンザスの姿にルッスーリアは呟きます。それに同意するのはマーモン。その横でレビィは憧れのまなざしでザンザスの仕事を見守っていました。
ここは並盛。一部の人たちにはオタクの聖地と呼ばれている場所。
その理由はザンザスや雲雀をはじめ大手サークルの作家達が集まる土地ゆえ。けれど彼らが直接顔を見合わせることはありません。彼らが出会うのはコミケという戦場であり交わすのは会話ではなくお互いが書いた作品という拳。
ハヤリーナという熱い絆を共にする猛者達は自分達が知らないところで繋がってたりするのです。
すごくかなり身近なところで。
ベルとスクアーロの別のお仕事は鈴木さんのサイトで読む事が出来ますw |
|
|
|