|
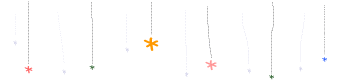 |
 |
僕には運命の出会いが4つある。
それは人より多いのか少ないのか分からないけれど、全てが僕にとっては忘れることの出来ない運命の出会い。
自分は人より幸せなんだと思ってた。
両親は僕の欲しいものなら何でも買ってくれたし、回りの大人たちも僕に優しく接してくれた。暖かなお家もあったし、広い部屋もベッドも玩具も何でも持ってた。おやつは毎日美味しいし、ご飯だっていつでも食べきれないくらい美味しいものが溢れてた。
でもそれがおかしいって事に気づいたのは半年振りに会った親に連れられていったイタリアでのこと。そこで出会った父親の仕事の関係者の家の子供と遊んだ時だった。
その家には僕と変わらないくらいの歳の姉妹がいた。姉は僕より年上の茶髪の勝気な子だった。妹は僕より年下の綺麗な銀髪の子供だった。二人ともおそろいのドレスを着てまるでお人形さんみたいで、けど遊び始めれば僕と変わらない幼い子供なのだと思い知らされた。かけっこに木登りにごっこあそび。姉妹は片言の日本語を話せると紹介されたが会話のほとんどはイタリア語だったから二人が何を話してたかは良く分からない。けど子供だった僕達には言葉なんて関係なかった。ただ一緒に遊べれば楽しい。姉妹の親もそれを見通して彼女達と僕を一緒に庭に放したのだろう。二人と過ごした時間はあっという間に過ぎていった。
けど僕にはその遊びの中で忘れられないことがある。それは最後に姉妹の姉が率先して始めたおままごと。男の僕にはあまり馴染みのない遊びだったけれど姉妹は女の子だけあって手馴れた様子で用意を始めた。なんとなく僕も内容は知っていたけれど自分から進んで参加したことの無い遊び。でもその遊びは衝撃的だった。母親に模した姉妹。不自由な日本語で内容を説明し始めた姉によると僕は妹が演じている“母親”の息子らしい。そして姉は近所の家の夫人。子供の役なら難しくは無いと説明されたが・・・僕は予想以上にその役に苦労した。
だって子供という立場に無縁だったことをその時思い知らされたのだから。
だって僕にとって両親は年に何回か会えるかあえないかの存在だった。姉妹の妹が演じた母親のようにご飯を作ってくれたり話相手を母親がしてくれたことは無い。少なくとも物心ついてから食事を共に取ったことだって無かった。最後に会話をした日だって覚えてない。一緒に手をつないでくれた日も覚えてない。同じベッドで眠った事だって無いのだ。
だから・・・おままごとのように甘やかしてくれる母親にどう接すればよいか僕には分からなかった。
ご飯を食べてお風呂に一緒に入って眠るまで絵本を読んでくれる。そんな時に僕はどうすれば良いのか・・・本当に分からなかったのだ。
だから僕はとうとう耐え切れずに泣き出してしまった。突然泣き出した僕に姉は慌てて大人を呼びに屋敷に向かい、妹はただ僕を抱きしめて頭を撫でてくれた。
「いたいのいたいのとんでいけー」
片言の日本語でのおまじない。姉妹は僕が怪我をしたか急病になったと勘違いしたらしい。でもその時、僕の頭を撫でて小さな体で抱きしめてくれた妹の顔に僕は胸が熱くなってしょうがなかった。
結局、そのときの姉妹とはそれっきりだった。泣き出した僕を見た両親は一緒に来ていた使用人に僕を任せるとそのまま何処かに行ってしまったし、イタリアという土地になれないと判断された僕は早々に日本に帰されてしまったから。
両親にまたあの姉妹とあうチャンスがあるか聞きたかったが次に両親にあえたのは1年後のことだった。その頃には取引先を変えていた親にそれ以上聞く事も出来なかったし、名前も知らない姉妹と僕が連絡をとる方法を幼い僕は知る由も無かった。
だからたった一度だけしか会うことが出来なかったけれど、あの時のおままごとは僕にとっては忘れられない思い出。そして銀の髪のあの子が演じてくれた“母親”は僕のその後を大きく変えた。あれが生まれて最初の運命の出会い。
小学校に上がってから僕は両親と会う機会が今まで以上に減った。僕が学校に通うようになったことも原因の一つだったが親が“僕のため”という名目でありとあらゆる習い事をさせたからだ。家でも表でも勉強。滅多に会わない両親は唯一の子供であった僕に期待してたらしい。だから僕もそれに答えようと必死だった。両親は僕が良い点を取れば一言でも「良くやった」と言ってくれたし、僕が賞状を持ってくれば一瞬だけでも僕に視線を送ってくれた。その僅かな関わりを求めて僕は努力を惜しまなかった。両親の望む良い子を演じればちょっとは見てもらえたから。
でもその反動からか僕は学校ではその良い子を続けられなかった。なにせ親が寄付金を出している学校だ。教師は僕の機嫌を伺うような奴らばっかしだったし、クラスメートも僕の親の影響を恐れて誰も逆らわなかった。だから我が侭を言いたい放題だったし、自由気ままにし放題。好き勝手なことばかりやってた。でもそんな事も最初だけ。最初は僕の親を恐れてちやほやしてくれた奴らも付き合いきれないと一人二人と離れていった。最期に残ったのは僕の親に気に入られようと気持ち悪い笑みを浮かべる“親切な大人”と、僕が持つ玩具や権限を欲しがる“仲の良い友達”だけ。
誰も僕を見てくれない。そんな人たちに囲まれてはじめて僕は自分という存在の空しさに気づい皆が欲しがるのは僕の親が持っている財産。皆が僕に見ているのは僕の親の影。皆が僕に優しいのはあの両親の息子という肩書きだから。
けどそれに気づいても僕はもう止まれなかった。家で演じる良い子にも、学校で演じる自由気ままな僕も。今更止められなかった。空しいと思っても。
「そんな我が侭ばかり言ってたら駄目ですよ」
そんな僕だから彼が言ったその一言を聞いて無意識に涙したんだ。
入江正一と名乗ったクラス替えをして最初に隣の席になった少年。彼は僕の瞳を眼鏡越しにじっとまっすぐ見つめていつもの様に我が侭を口にした僕にはっきりとそう言った。
驚愕だった。僕も周りのクラスメートも担任の教師も。彼以外の教室にいる人物すべてが彼の言葉に驚いていた。そしてその言葉に涙をこぼした僕にさらに教室はパニックになったのだ。
それからのことは覚えていない。ただ久しぶりに泣いて頭が痛くなったことは覚えている。だけどあの後どう収集をつけたかは僕の記憶には残っていなかった。ただアレが縁で僕は“正ちゃん”というかけがえの無い存在を手に入れられたんだと思っている。
彼は色々周りの奴らと違っていた。僕が我が侭を言えば怒ったし、やっちゃいけないことにははっきりと意見した。僕の考えに賛同もしてくれた時は力強い味方となってくれたし、なにより・・・損得関係なしに僕の傍にいてくれた。
「白蘭さんは・・・まったくしょうがないんですから」
いつもそういって呆れながらもため息混じりに僕の隣にいてくれる。正ちゃんのお陰で僕は初めて“僕”として見て貰えた。これが二つ目の運命の出会い。
そしてそれから数年後。あれはある本屋でのことだった。
お小遣いを握り締めて正ちゃんとやってきた街角にある本屋。初めて自分の持ったお金で買い物をするという経験に心をときめかせていた自分が手に取ったもの。
・・・それは一冊の漫画本だった。
表紙には可愛らしい女の子の絵が描かれていた。
タイトルも聞いたこと無ければ内容も知らなかった。
なによりそれを手に取った瞬間、正ちゃんは破願してた。
でも僕はその本を手にとらずに入られなかったんだ。だって表紙に描かれていた愛らしいドレスに身を包んだ女の子は・・・僕に母親というものを教えてくれたあの子にそっくりだったんだから。
綺麗な綺麗な銀色の髪と緑色の瞳。お人形のようなその容姿はあの日の僕の記憶にリンクして心を離さなかった。中身なんて関係ない。ただこの子に傍にいて欲しい。そう思った僕は正ちゃんに教えてもらったレジに行き始めての買い物をしたのだ。
その時買った漫画本のタイトルは『虹の都のハヤリーナ』。この一冊は僕の3つめの運命の出会い。
ハヤリーナと出会い僕は翌日には全ての巻を集めるまでになっていた。心を奪われたハヤリーナという少女と今まで知らなかった漫画という表現方法は衝撃的で、百花という敵とハヤリーナとの話や活字とは違う目の前に広がる世界に僕は夢中になっていた。
でも・・・そのせいでおろそかになっていたのかもしれない。気がついたら僕が演じる“良い子”は親の望む“良い子”から少しずつ軌道が変わってしまっていた。
正ちゃんと出会い、家でも僕を見てもらうためにはっきりと物を言うようになった僕に両親は言葉をかける機会が減っていた。
自分の好きなことのために自分の時間が僅かでも欲しいと願った僕に父親は落胆していた。
あの姉妹が教えてくれたような家族の関係を望んだ僕に母親は顔を向けることすらしなかった。
両親がどんな僕を望んでたのかは今となっては分からない。けど一度だけ父親が電話で言っていた『六道家の子供に負けるな』という言葉が僕の脳裏に焼きついていた。うちと対立する名家・六道家。後に僕と変わらないくらいの歳の子供がいると聞いて、僕は比べるための道具にされてたのかとぼんやり思っていた。
けど僕は最後まで頑張ったんだ。
すこしでも親に見てもらおうと。
小学校を卒業間近に迫ったある日、珍しく家にいた父親は僕の部屋にあった漫画を全て燃やした。こんなもの必要ない、の一言だった。
母親は隠していた僕の書いたイラストや漫画の書かれたノートを見て、燃え盛る炎の中に投げた。呆れながら・・・くだらないと言い放った。
2年ぶりに直接会った両親は、徹底的に僕を否定したのだ。精神的にも目に見える形でも、全てすべて全て。
そう、父親も母親も僕を否定し僕を見ようともしてなかったんだ。理解しようとも話を聞こうとも・・・僕を思おうともしてなかったんだ。
燃え盛る炎のなかで灰となっていく僕の思いのこもったノート。真っ赤に燃やされ消えていく表紙に描かれたハヤリーナの笑顔に僕は誓った。
もう、我慢しないと。
僕は話を聞かなかった父親の胸倉を掴んで思いのたけを叫んだ。逃げようとする母親の腕を掴みその顔を見つめながら僕は訴えた。僕の思い。僕の願い。今まで抱え続けていたもの。そして最後の最後で僕は悲鳴のような声で叫んだんだ。
「お前達なんか家族じゃない」
母親の涙。父親の怒り。
翌日の朝には家を出ていた両親は僕への回答を使用人に言付けていた。
「中学へ入学すると同時にこの家を出ろ」
と。僕はその言葉を聞いた瞬間に大声で笑った。可笑しくてたまらなかった。
結局、両親は逃げたんだ。二人の望んだ形とならなかった息子に逃げ出したんだ。
数ヵ月後には宣言どおり両親は僕に家を与え、僕を家から追い出した。
表向きは一人で暮らして反省しろとか成長しろとか言うことらしい。でも裏を返せばすぐに弱音を吐いて泣きついてこいと・・・自分たちのところ意外に僕の居場所はないのだと言ってるのと同じだった。実際、今まで使用人達に囲まれてきた僕には一人で暮らしていけるだけのスキルは無い。生きていくために必要な金だけは腐るくらい親はくれたけれど。でも僕は帰る気はなかった。あの家族の下には。
引越しの当日、家をでる僕の前に父親も母親も姿を見せなかった。ただ馴染みの使用人が何人かは涙ながらに見送ってくれたのだ。
そして新しい家で出迎えてくれたのは正ちゃんと引越しの手伝いに来てくれた彼の家族だった。
「お帰りなさい、白蘭さん」
正ちゃんの言葉に僕は笑顔で大きく頷いた。
そして現在。家を追い出されて数年たった今。
僕はとある人物の膝の上に頭を乗せながらあの頃では考えられないくらい穏やかな時間を過ごしている。
「白蘭さん。あまり隼人さんを困らせちゃ駄目ですよ」
ぬくぬくと膝に顔をうずめ幸せそうにしている僕の隣で注意してくるのは正ちゃん。
「まぁいいじゃねーか。ちょっとくらいは甘えたって」
そう言いながら僕に膝を提供して頭を撫でてくれるのは僕が『ママ』と慕う人物。
「隼人さんもあまり甘やかさないほうが良いですよ。嫌な時は嫌って言わないと」
「・・・うーん。別に嫌なわけじゃないし。なんか幸せそうなこいつの顔見てると体が勝手に動くような感じ?」
「・・・・・母性本能って奴ですか?」
「・・・・・・・・・・・俺、男だしこいつは俺より年上なんだけど・・・な」
苦笑しながら優しく優しく僕の白い髪を撫でてくれる。
家を出て僕はすぐに白い髪に染めた。それは僕の愛するハヤリーナの漫画に出てくる百花というキャラに自分を重ねたからだ。複雑な家庭環境に育って僕同様に親の愛に恵まれなかった彼。そしてハヤリーナは彼にこう言ったのだ。
「ごめんね。あなたのママになってあげられなくて」
優しいハヤリーナはそういって百花を抱きしめていた。僕の忘れられないワンシーンだ。
あの場面を見た瞬間から僕はハヤリーナに母性を求め、百花に自分の姿を見ていた。
そして見上げる今。僕の瞳には銀の髪に綺麗な緑色の瞳で優しく僕を見下ろす人物の姿が映っている。
「隼人ママ」
自然に零れた言葉に彼は困ったように笑いながらもそれでも僕を突っぱねようとはしなかった。横でその様子を見ていた正ちゃんもそんな僕たちの様子に何か言いたそうだったが、最後は穏やかな笑みを浮かべ見守ってくれている。
綺麗で優しく僕を抱きしめてくれる隼人ママと、厳しくも穏やかに見守ってくれる正ちゃんパパ。
幼い頃にあの姉妹と演じた家族の姿を僕は今、手に入れたんだ。
それはあのときのように所詮は“ごっこ”遊びなのかもしれない。けど僕が手に入れたこの空間と穏やかな時間はけして嘘ではない。
ゆっくりと撫でられる髪の感触に瞼が重たくなっていく。うとうととし始めた僕にブランケットをかけてくれた正ちゃん。小さな声で子守唄を歌ってくれたのは隼人ママ。
僕はそんな二人に促されるまま温かな眠りに身を任せた。
「随分と、隼人さんは白蘭さんのあやし方手馴れてますよね。下のご兄弟とかの面倒を見てたことがあるんですか?」
「いや・・・俺は姉貴しかいねーんだけどさ、その姉貴が“たまには妹が欲しい”とか分けの分からないこと言っては俺に自分の服着せて女の子の遊びを無理やりさせたんだよ。だからかな。おままごととか良くさせられたし、他所の子供が来ては俺に母親の役とかやらせてたし」
「あー・・・なるほど」
夢の世界で聞こえた二人の会話。僕の4つ目の運命と思っていた隼人ママとの出会いは意外に必然だったのかも。
遅くなったけれど、僕は今・・・子供を演じている。
番外編シリーズで多分唯一と思われるシリアス話。次回からはまたお気楽ですw |
|
|
|