|
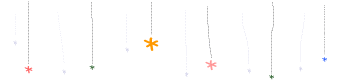 |
 |
白蘭さんの執務室にはマフィアのボスの部屋にしては不自然な青いボールが一つある。埃と時間で所々が茶色く汚れた青いボール。それを腕に抱き楽しそうに眺めるのがこの部屋の主・・・白蘭さんの日課だった。
「あぁ・・・またですか」
そして今日も午前中の仕事を終わらせた白蘭さんは青いボールを抱きしめて幸せそうな笑みを浮かべたままソファで丸くなっていた。笑みを浮かべる口から漏れるのは穏やかな寝息だけ。ゆっくりと肩を上下させながら母胎の中の子供のように身体を丸め安心しきった様子で過ごしている。
僕はそんな白蘭さんの姿に苦笑しながらブランケットを彼の身体にかけた。すると白蘭さんは無意識にかブランケットに顔を埋め小動物のようにさらに身体を丸くする。
「まったく。これがマフィアのボスだなんて信じられませんね」
幼子のようなその姿。それは始めて僕と彼が出会った日を・・・なんとなく思い出させた。
僕が始めて白蘭さんに出合ったのは僕が中学生で白蘭さんが幼稚園のときだった。母親に連れられ郊外の公園にやってきていた白蘭さん。そんな彼が遊んでる最中にボールから眼を離してしまい、見失って探していたそれを届けたのが僕だった。でもただそれだけの係わり合いなら通りすがりで終わったのかもしれない。けど僕はその時にボールを一緒に探していた白蘭さんが『ママ』と呼ぶ人物に眼を奪われてしまったんだ。僕が白蘭さんにボールを手渡すとその人は笑顔でお礼を言い立ち去っていった。綺麗な・・・美しい人だった。年上の、しかも子持ちの女性にこんな感情を覚えてしまうなんて本当ならおかしいのかもしれない。けど僕は一瞬にしてその女性に心を奪われてしまっていた。
翌日から僕は用が無くてもその公園を訪れるようになっていた。また、なんてチャンスはそうそう無いのかもしれない。けど僕は諦められなかった。名前も知らない人だったけれどもう一度会いたいと思ってしまったから。そしてそんな僕を神は見捨てなかった。僕がその公園に通い詰めるようになって数日目。白蘭さん達はもう一度公園に遊びに来てくれたのだ。
通りすがりを装って声をかけると白蘭さんは覚えていたらしく笑顔で駆け寄ってきてくれた。そして成り行きで遊び相手になる事を約束すると申し訳なさそうにあの人は僕に再びお礼を言ったのだ。
「ありがとう。俺は・・・隼人。こいつは白蘭だ」
「僕は入江正一です」
「正一・・・じゃあ正ちゃんだな」
この時、苗字じゃなくて名前を名乗った事に違和感を感じたけれどその時の僕にはそんなこと関係なかった。ただ僕は隼人さんの名前を知れたことに舞い上がってしまっていたから。その後白蘭さんに腕を引っ張られ彼と遊び懐かれたことで僕はこの不思議な親子との縁を結ぶ事が出来た。そして何度か共に過ごしているうちに僕は白蘭さんの兄のような父親のような不思議な立場となり、隼人さんともそれなりの関係を築く事ができたのだ。
隼人さんと過ごしたあの日々は本当に幸せだった。それは僕にとっても白蘭さんにとっても・・・そして隼人さんにとってもそうだったと僕は信じてる。穏やかで楽しい時間。最初は隼人さんとの縁を作るために近づいた白蘭さんだったけれど懐かれ慕われるうちに彼はかけがえの無い大事な存在になっていたし、隼人さんも共に同じ時間を過ごしているうちに彼女の中の魅力にどんどん惹かれていった。そんな二人との思い出の時間は本当に本当に僕にとって大事なもの。それの終わりが突然で何の前触れが無いものだったとしても僕にとっては大切な記憶だった。
別れの言葉も継げずに僕達の前から姿を消してしまった隼人さん。
保護者のいなくなった白蘭さんはその後直ぐに隼人さんの知り合いだと言う男の手で養子に出されてしまった。
でも僕は二人が消えた事が信じられなくて諦められなくて何度も何度もあの公園を訪れたが・・・勿論、あの場所で二人に会うことは出来なかった。
隼人さんは白蘭さんを捨てたのだろうか。
否。そんな事は考えられない。隼人さんは白蘭さんを大事にしてたし本当の親子じゃなくてもそれ以上の絆で結ばれていた。
なら隼人さんは死んだのだろうか。
否。それも考えられない。僕は出来うる限りの手段を要して調べぬいたがあの日の並盛近辺で彼女に該当するような死者はいなかった。
僕はあらゆる可能性を求めたが恐ろしいくらいに隼人さんへの足取りはプツリと途絶えていた。彼女の私物も、彼女がいた証も、彼女が過ごした証明も何処にも残されていなかったのだから。まるで最初からそこに『隼人さん』という存在がいなかったかのように。白蘭さんを連れて行った隼人さんの知人の男も探してみたがどうしても辿り着く事が出来なかった。そう・・・不自然なくらい、隼人さんに繋がるものが残されていなかった。
もしかしたら隼人さんは僕が見た幻だったのだろうか。白蘭さん達と過ごした日々は僕の夢だったのだおろうか。あまりの手がかりの無さに諦めかけていた数年後、僕の元に一通のエアメールが届いた。僕は差出人の名前を見て驚いた。それはあの日以来会うことのなかった白蘭さんからのものだったからだ。
最期に別れてから白蘭さんは隼人さんの知人の男の紹介でイタリアの裕福な家庭に養子として引き取られたらしい。優しい両親に囲まれ今は何不自由なく暮らしているとのことだった。同封されていた写真には僕が知っているのより成長した白蘭さんと優しそうな外国人の夫婦が写っていた。幸せそうな家族写真。けど、僕はそんな写真の中の一点に気がつくと直ぐに返事を出すために便箋を広げた。
写真の中で白蘭さんが大事そうに持っていたもの。それは始めて白蘭さん達と出会った日に僕がわたしたボールに違いなかったのだから。青い青いボール。あのボールを手渡した時の白蘭さんの嬉しそうな表情もお礼を言いに来た隼人さんの笑顔も僕は鮮明に覚えている。僕は久しぶりに見た隼人さんのいた証に興奮を止められなかった。そして震える手で僕は白蘭さんに手紙を書いたのだ。
“僕とあなたが過ごした日々は嘘ではないですよね”
下手な事を書けば消されてしまうかもしれない。だから僕は直接的な表現は避けてたった一文こう書いた。
それ以外は平凡な内容で埋めて、当たり障りのない文章で一番伝えたい言葉を隠した。そして暫くたってから届いた返事に僕は涙したんだ。
“『正ちゃん』と始めて呼んだ日を僕は今でも覚えてるよ”
と。
それは端から見れば何気ない一文だったのだろう。けど僕にはそれだけで充分だった。だって僕を『正ちゃん』と呼び、白蘭さんにそう言わせたのは隼人さんだったから。あぁ、彼女がいた証は確かにここにある。僕はこみ上げてきた思いを込めて直ぐに返事を書いた。
それから数年間。僕が白蘭さんに会いにイタリアに渡るまで文通は続いた。紙の上でも構わないから、隼人さんの証明を分かち合いたい。彼女がいた証は今では僕と白蘭さんの記憶でしかなかったのだから。あの日々が嘘じゃないと信じるためにも、お互いの記憶を確認しあうためにもそれは必要な行為だった。
そして親の期待に答え一流大学を卒業した僕は『世界を広げたい』とだけ言い残し単身イタリアに渡った。イタリアでは立派に育った白蘭さんが出迎えてくれた。その腕の中にはあの日も変わらない青いボール。それだけが僕と彼を支えてくれた唯一の品だった。
その後、養父の跡を継ぎ一マフィアのボスとなる事になっていた白蘭さんをサポートすることになっていた僕は力をつけるために全力を注いだ。慣れないイタリア語も必死で覚えたしマフィアという特殊な組織の中で生き抜くための術も得た。そして見事にボスの座を手に入れた白蘭さんの右腕となりファミリーの力を広げるための努力も惜しまなかった。
全ては・・・隼人さんへの手がかりを得るために。人一人の情報を得るために大げさかと言われるかもしれない。けれど彼女のいた証が塵ひとつ残されていない事、そして繋がる糸が全て断ち切られていたことで僕は大きな力を感じたんだ。そしてそれは白蘭さんも同様だった。
隼人さんは大きな力で僕達の手の届かない存在になってしまっている。悪意があってのことか、隼人さん自身が望んでの事か。それは分からない。ただ僕達の思いは純粋で根強いものだった。
ただ、もう一度彼女に会いたい。
それだけが僕らの願いだったのだから。
そして現在。ミルフィオーレという巨大組織となった今でも僕達は彼女を見つけられないでいる。あれから10年近くたった。あの時の事を考えれば隼人さんもそれなりの年齢になっているだろう。僕と白蘭さんが大人になったように彼女もそれなりの年月を重ねてきたはずなのだから。
でもどれだけ姿が変わろうとも、歳を取ろうとも僕達は彼女を見失わない自信がある。一目合えば絶対に彼女と分かる。僅かな時間しか過ごしていない僕達だけど隼人さんとの絆はそれだけ深いものなのだ。そう僕は信じてる。そしてその再会に向かうため僕は今日も僕は努力を惜しまないのだ。
しばらく寝入っている白蘭さんをながめながら思い出に浸った後、僕は腕時計から零れたアラーム音に意識を元に戻す。そうだ隼人さんのために僕は努力を惜しまない。それだけは誰に求める事の出来ない確かな思い。僕はもう一度そう心の中で呟くとソファで眠っている白蘭さんの耳元で叫んだ。
「いつまで寝てるんですか。約束の時間に遅刻します。きっと隼人さんは遅刻するような子は嫌いなはずですよ」
その言葉を聴いてがばっと飛び起きる白蘭さん。
「や・・・やだ!起きるから・・・うぅ・・・ママには内緒にしといて」
「はいはい。あと5分で用意が終わったら隼人さんには秘密にしておいてあげますよ」
「わかった。正ちゃんありがとう!」
そう叫ぶと部屋に備え付けてある洗面台に向かう白蘭さん。飛び起きても大事なボールは忘れないらしく青いそれはソファの上で転げ落ちることなく鎮座していた。
「そういえばね、正ちゃん」
ボールを眺めている僕に洗面所から白蘭さんが声をかける。
「さっきママの夢を見たんだ」
それは偶然なのだろうか。さっきまで隼人さんの事を考えていた僕と夢の世界にいた白蘭さんとの奇妙なシンクロに不思議な感覚を覚える。
「ママの前で始めて泣いた時の夢でね・・・ママが始めて僕を叩いた日の夢。あの日、僕がボールに夢中で車に気付かなくてさ轢かれそうになったときにママが慌てて駆けつけて助けてくれたの。それで何が起こったのかわからない僕の頬をママが叩いたんだ。泣きながら一度だけ叩いたんだ。そしてこう言って抱きしめてくれたんだ・・・『白蘭がボールが大事なようにママも白蘭が大事で、白蘭がボールを無くしたくない様にママも白蘭を失いたくないんだ。白蘭はボールが大好きだろう?壊れたり、無くしたりしたら嫌だろう?でもそれ以上にママは白蘭が大好きで大事なんだ。きっと今叩いた白蘭のほっぺた以上に心が痛くなるし、悲しくてしょうがなくなっちゃうから・・・それだけはどうか忘れないで』って」
「・・・・白蘭さん」
夢の内容と隼人さんの言葉に胸が熱くなる。やっぱり信じていいんですよね。あの優しい日々を。そして隼人さんが自らの意思で僕達の前から姿を消したわけではないと。それだけの愛情を白蘭さんに向けてくれた隼人さんなのだから。きっと深い事情があったに決まっている。
「ママに早く会いたいな」
「えぇ・・・そうですね。早く僕達の手で会いに行きましょう」
「うん」
「その為にも今日の会合は必ず成功させてくださいね。相手はマフィアの中でも格式、伝統、規模においてトップクラスな相手ですから」
「わかった。絶対成功させるよ」
ママのために。
隼人さんのために。
僕達の思いが重なる。そう彼女と別れてから10年近くたった。でも僕達の思いはあの日から何一つ変わらない。
「さぁ、行きましょう」
白蘭さんを促し会議室に向かう。全ては夢を叶えるために。もう一度あの日々を取り戻すために。
待っていてくださいね、隼人さん。
僕はそんな願いを込めて会合の相手であるボンゴレファミリーのボスとその右腕が待つ会議室の扉を開いた。
|
−そして10年越しの物語が動き出す。
純粋な子供たちの願いと、ある一人の人物の野望を糧にして。 |
未来の正ちゃん視点。会合の相手は勿論あのボスですw |
|
|
|