|
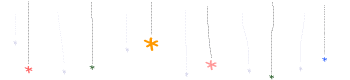 |
 |
英語は何時も赤点。
もちろん英会話なんてできるはずもないし聞き取りだって出来るはずが無い。
だから、ツナは途方にくれていた。
「イッツ オ スオーメ プレーゴ?」
幼い舌で紡ぎだされる言葉はどう聞いても日本語でなくって。
「あのね・・・俺、英語喋れないの。わかる?」
「イッツ オ スオーメ プレーゴ?」
「また・・・それ・・・・」
しかも相手は日本語を理解できないようで、なんかよく分からないけれどニコニコと笑いながら問いかけてくる様子からして懐かれたようで、さらに手を握られたまま振り放す事など出来るわけも無くってツナはがっくりと肩を落としながら目線をあわすように座り込んだ。
「とりあえず、君を家に送り届けなきゃ・・・かな」
「?」
「家。ホーム。僕の言ってる事分かる・・・?」
きょとんとして見上げる少女にツナはガクリと肩を落とす。
完全に通じてない。そもそもツナの話している内容の半分以上は日本語だし。必死に頭から片言の英語を引き出すが単語ばかりで上手く繋がらないし。
こんなことなら真面目に勉強しとくんだった。
そう思って瞬間、後から声をかけられた。
「チャオっす」
「その声は、リボーン?」
はっとして振り向けば、そこにはいつからいたのかニヒルな笑みを浮かべた赤ん坊・・・リボーンが立っていた。
ツナの家庭教師兼殺し屋兼マフィアとしても教育係。
三つの肩書きをもつ赤ん坊の突然の登場にツナは恐怖を覚えながら半泣きで助けを求める。
「リボーン、お前ならこの子の言ってる事わかるだろ」
「この子?」
そう言われてリボーンはツナの指差す少女に声をかける。
ツナの腕を掴み、不思議そうに琥珀色の瞳で自分を見つめる少女。
少し怯えた様子の少女だったが、リボーンと2,3言会話を交わすと顔を輝かせツナの手を掴みながらピョンピョンと跳ね始めた。
「どうしたの、この子?」
「どうしたもこうしたも、コイツは俺の知り合いの子供だ」
「えーーーーーー!?」
リボーンの言葉にツナは絶叫しながら少女を見つめる。
リボーンの知り合い。と、言う事はまさか・・・。
「この子も殺し屋!?」
「そうだぞ。イタリアから来たばかりで、まだ日本の言葉にも土地にも慣れてないそうだ。で、なかなか帰ってこないからコイツの親から捜索を頼まれたんだ」
「そうなんだ・・・でも、こんな小さいのに殺し屋・・・」
「小さいっても3歳だけどな」
十分、小さいよ。
その言葉を胸にしまいつつ、思えばリボーンなんか1歳だしなと思いながらツナはまだご機嫌な様子で自分の手を掴んでいる少女を見つめる。
イタリアから来たなら自分も相手も言ってる事を理解できないわけだ。
そもそも助け上げたときに「サンキュー」とか聞きなれた言葉ではなく「グラッチェ」という聞き馴染みの無い言葉を使われた時点で気づくべきだったのかもしれない。
「で、この子、さっきから俺になんて言ってるの?」
「Il suo nome, prego?イタリア語で“あなたの名前を教えて”って言ってるんだ」
「あ、なるほど・・・。じゃあ自己紹介してた方がいいかな」
「その必要は無いぞ。俺が先に教えといたからな」
リボーンの満面の笑み(?)にツナは嫌な汗が流れたのを感じる。
そして少女に目をやると彼女も満面の笑みを浮かべてツナの名を呼んだ。
「じゅーだいめ」
と。
「ボンゴレの新しいボスに相応しい名だな」
「うぎゃーー!変な言葉教えないでよ!!!!」
「じゅーだいめv じゅーだいめvv」
名前を呼びながら抱きついてくる小さな体にツナは眩暈を覚える。
小さなことからコツコツと。地味にボスとするべく周りを固め始めたリボーンに怒りと呆れと相変わらずな恐怖を覚えながらツナは大きく溜息をつくのだった。
だが、ツナはまだ知らない。この少女がすでに自分の部下に加わっていた事を。
「まずは一人目のファミリーゲットだな」
その影でリボーンが笑っていたことも。
|
|
|
|