|
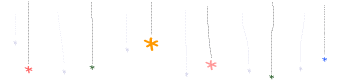 |
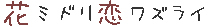 |
奴と俺との共通点。それは今も昔も唯一つ。
親に男みたいな名前をつけられた女の子。
たったそれだけだったと思う。けどそれだけの理由で幼稚園の年少組から腐れ縁ともいえる付き合いを続けてきた俺達は中学生となった今も奇妙な関係を続けている。
友達でもない、他人でもない。俺としては悪友というなの親友かと名づけてきた絆だがそれを聞いた奴は鼻で笑って俺を見下すように諭した。
「あのね、僕たちの関係は“恋人同士”っていうんだよ」
心のそこから哀れむような、馬鹿にするような言い方をしながら恭弥は向かいのソファで足を組み直す。足を組む瞬間にスカート越しから奴の黒い下着が見えたが奴は特に気にした様子は無い。逆にそれに気付いて注意しようとした俺にさらに小馬鹿にしたような視線を向ける。
「なにか言いたそうだね」
「言ったら怒るか馬鹿にするか殴るくせに」
「うん、分かってるじゃない。頭の良い子は嫌いじゃないよ」
そう言いながら“自称”俺の恋人、恭弥はご褒美と言わんがばかりに俺に近づき抱きしめた。俺は座ったままで奴が立ったせいか俺の顔が奴の形のいい胸に埋もれる形になったが奴はそれも気にしない。ブラウスの隙間からパンツに合わせたこれまた黒い下着が挑発的に俺の目に入ってきたがそれも奴は気にせず薄笑いを浮かべた。
「隼人はダメだよ」
「言うと思った」
「僕だから良いの。君はダメ」
何がダメで何が良いとか、いうなれば俺の下着の話。
以前、奴の忠告を聞かずに黒い下着なんかで登校したら“好みじゃない”の一言で応接室に連れ込まれ、そのまま一日下着無しという屈辱を味あわされた。
「君は僕の恋人なんだから僕の好みの格好をして、僕の好みの姿でいればいいんだ」
「自分勝手、自己中。自分は黒の下着着てるくせに」
「僕は良いの。似合うから」
でも君はダメ。何度も同じ言葉を繰り返しながら俺をぎゅうと抱きしめる。
少しでも恋人というなら俺の意見を聞けよとか、俺の意見も受け入れろと叫びたいところだけど文句を言いつつも俺も恭弥に少しでも好かれたいから奴の好みの格好をしてしまう。
あぁ、そうか。こう考えると俺もコイツが好きなんだっけ。
なんとも答えが出てしまえば、不思議な気持ちになったが奴の胸に抱かれても相思相愛特有の幸せな気分になれないのは俺がひねくれてるせいだからだろうか。それともコイツがひねくれているせいだろうか。
「明日は苺の下着がいいな」
クスクスと俺の髪をなで機嫌のよさそうな笑みを浮かべる恭弥。
そういうコイツは明日も黒い下着で、きっとその横に立つ俺はこいつ好みの苺の下着を着ているのだろう。
それが幸せな恋人同士の姿なんて、きっと誰も気付かない。
それでも俺達はなんとなく満足してるのだから、幸せというものも俺達同様ひねくれていると思わずにいられなかった。
勢いで書いた百合雲獄。会話の内容が下着だけってどうなんだろう・・・。 |
|
|
|