|
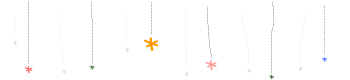 |
 |
彼女の世界は僕だけだった。
僕の世界は彼女一色だった。
初めて出会ったこの世界で唯一僕と対になる存在。それって言うなれば平等な存在ってことだよね。僕と同じ、僕と同じ神様として生まれた子。
僕は『祝いの子』で君は『呪いの子』だけどどんな形であれ神様には変わりないはずだから。
この世界が変わるまで、君と僕だけが同じ存在。
初めて出会ってから時が経つのも早いもので、隼人は先日無事に16の誕生日を迎えた。
「おめでとう隼人」
僕はそう言うと檻越しにプレゼントを入れる。けれど受け取る隼人の顔は浮かない感じ。それは毎年この日になると決まってそうだから僕はあまり気にしてなかった。
「・・・・・・・・・・・おめでたくないよ」
また一年生きながらえただけだ。溜め息混じりに言う彼女は縋るような視線を僕に送る。この後続く言葉も毎年同じ言葉。
「白蘭、何時になったら俺を殺してくれるんだ」
「そのうち・・・かな」
「いつもそればっかりだ」
いつか必ず、君を殺してあげる。それは始めて隼人と向かえた誕生日に僕が贈ったプレゼントだった。いくつプレゼントを贈った中で一番喜ばれたプレゼント。その呪われたプレゼントを隼人はずっと忘れていない。
去年贈った花は枯れてしまった。一昨年送ったドレスは虫食いで着れた物ではない。5年前送った本は雨漏りのせいで字のほとんどが溶けてしまった。そんな中で唯一形を変えることなくのこっているプレゼントでもあるのかもしれない。
「早く、白蘭の手で殺してほしいな・・・」
陶酔気味にうっとりと呟く彼女。自らが生まれた日に死を望む。
普通なら考えられない思考回路だが彼女の境遇からしてみればそれを望むのもしょうがないのかもしれない。長い年月を邪神として疎まれ、光の届かない地下牢に閉じ込められ、人間としてのまともな扱いを僕以外からまともに受けていない彼女。生まれ育った環境を考えればまともな精神を残すほうが困難だろう。むしろ狂っているくらいが正しい精神状態なのかもしれない。
この箱庭の世界と歪んだ進行で繋がれた人生。その境遇からの唯一の救いが“死”なのだ。
「けど、隼人が死んだら僕は悲しいな・・・」
本心でそう言うけれど彼は不思議そうに僕を見つめるばかり。僕のいってる言葉が理解できないんだろうね。
「白蘭は変なこと言うんだな」
変な事をいってるのは隼人のほうだと僕は思うけれど、僕以外が隼人の“生”を望んでいないことは悲しい現実。だから“変”なのは僕で、“正しい”のは隼人にあるのだ。
同じ世界に生まれて同じ国で育った僕と同じ存在。なのにどうしてこんなに考え方が違うのだろう。僕は悲しくて檻越しに隼人の頬に触れた。成長した僕の手では檻から腕を伸ばす事が出来ず僅かな接触しかはかる事が出来ない。
「この手が俺を殺してくれるんだな」
嬉しそうに擦り寄る彼女。安心しきったような表情で唯一感じられる人肌である僕に甘えてくる。箱庭の世界で純粋すぎる狂気と育ってきた愛しい人。その頬はあたたかくて、潤しく、・・・・僕の心を凍らせるのに充分な温もりだった。
君だけが僕と同じ存在。対になる存在。平等な存在。
神様の生まれ変わりとして生まれてきた僕らなのに、どうしてこんなに違うのだろう。
檻の外は向こう側なのかこちら側なのか。
狂っているのは僕なのか彼女なのか。
救いなのは死なのか生なのか。
鏡あわせの様な問答の中で僕達は遮られている。
ただ彼女がいて僕がいる。それだけが絶対の事実。
まってて隼人。君のために僕が正しい世界を作って見せるよ。
それまで檻の中で待ってて。
狂っているのは世界のほうだから。
生きて生きて、ただ僕のために生きて。
僕の中での答えは何時だって決まっていた。
どうもこのシリーズは獄が病んでるっぽい; |
|
|
|