|
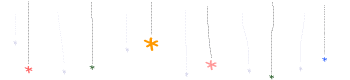 |
 |
(ヤンデレ―正一編)
人間に生まれつきあると言われる三大欲求。
「性欲」「睡眠欲」「食欲」
性欲。これは愛する彼女に反応している僕にはまだ残っている。男としての本能はしっかりのこっているし彼女を抱きたいと思う。欲情だってするし下世話な話、立つものは立つのだ。だからまだ大丈夫。
睡眠欲。彼女は何かというと寝不足気味な僕を心配しているけれど休日の日にむさぼるように眠る僕にはまだ残っている欲求だ。仕事のときは熟睡は程遠いけれど彼女の横で安心して眠れるのだからまだ大丈夫。
そして食欲。最近の僕はこれに対して自信が無い。おなかが空かないわけではない。喉の渇きだって覚えてる。美味しそうな食事を見れば心動かされるし、綺麗に盛り付けられたご飯を見れば美味そうだなって思う。でも手が出ない。口に運んでも飲み込めない。喉に流し込もうとすると襲い掛かってくるのは言いも知れない嫌悪感。
人間が生きていくために必要な行為だと分かっているのに、僕はそれが出来なくなってしまった。
「正一・・・」
悲しげな目で吐き続ける僕を見下ろす隼人。吐き出した残骸を見て涙を零しそうになっている恋人に僕は嗚咽しか口から出す事が出来ない。ごめんね、とか悪いね、とか謝りたい気持ちはあるのに僕は涙を流しながら胃の中のものを全て出す行為に集中することしか出来なかった。
水と共に流れていく彼女の手料理だったもの。この日、僕はとうとう彼女の手料理すら食べれなくなってしまった。
食への恐怖。それが始まったのは何時からだっただろう。
美味しいご飯が食べたい。
綺麗な水が飲みたい。
安全な食事を取りたい。
それらにこだわり始めた時全てが変わった。水道水が飲めなくなった頃はまだ可愛いほうだった。食堂で他の人と同じモノが食べれなくなった内は逃げ道は用意されていた。原材料のハッキリしないモノが飲み込めないときにも僕は今ほど苦しんではなかった。
だって僕の傍らには恋人である隼人の姿がいたから。出来たばかりの年上の彼女。一般的な食事が取れない僕に対して彼女は寛容だった。水道水が駄目ならと高い金を払ってミネラルウォーターを揃えてくれたし、人と同じ食事が取れない僕に彼女は自ら手料理を作ってくれた。僕に合わせて原材料が分からないものは使わなかったし、農薬やらなんやらにも恐がる僕のために家庭菜園まで開いてくれたのだ。ここまでやってくれる恋人はそうそういないだろう。でも彼女はなんの苦労も僕に感じさせないまま全てをこなしてくれた。ただ、僕のために。
でも、そんな彼女の愛の塊である食事を僕はとうとう吐き下した。一度流れ出すと止まらない恐怖は僕の身体を侵食していく。
この時だけ、なら問題は無かった。けれど勢いのついた僕の食へのこだわりは最後の堤防すら破壊してしまったのだ。
「正一・・・いいんだ無理しないで。食べれるようになったら食べてくれ」
悲しげな笑みを浮かべながらバケツを抱えて部屋に閉じこもる僕におかゆを届けてくれた隼人。おかゆの水は天然水。米だって彼女が汗水流して作ってくれた無農薬米。味付けに使っている塩だって彼女がわざわざ天然素材だけを使って作ってくれたものだ。
なのに・・・今の僕にはその匂いすら気持ちが悪い。頭がくらくらして口の中にすっぱい胃液の味が広がって僕はまたバケツを抱えた。
翌日、部屋の外に放置された冷めたおかゆを見ても彼女は何も言わなかった。僕も何もいえなかった。昼に温めなおしたおかゆを一口も手をつけなくても、気を取り直して作ってくれた別のおかずをみて僕が口元を押さえても彼女は何も言わなかった。ただ悲しげに眉を伏せて、
「気にしなくていいから」
と儚い笑みを浮かべるだけだった。
彼女の手料理が食べれなくなって一週間経った頃。ろくな食事を取らずに憔悴している僕に始めて笑顔以外の表情の彼女が言った。
「正一は俺を愛してるか?」
「・・・・愛してますよ。勿論でしょう」
こんな僕にここまで尽くしてくれる隼人を僕は最高の彼女だと思っている。それは偽りの無い言葉だった。
「俺も正一を愛してるよ」
「隼人・・・ありがとう」
隼人からの愛の言葉に僕は頬を緩める。肉体的には疲れ果てていたけど精神的に癒された瞬間だった。
「だから、これが俺の愛の証・・・だ」
隼人がそういった次の瞬間、僕の視界に紅が入った。彼女が突然自らの足に包丁を指したのだ。苦痛に顔をゆがめる彼女。慌てて止血しようと僕が駆け寄るが彼女は真顔で制止して包丁をさらに深く突き刺した。
「なにも信用できないというなら俺を信じて。恐くて何も口に出来ないというなら俺の血肉を食べて・・・」
彼女の言葉に僕は顔を蒼くすることしか出来ない。でも次の瞬間、僕を心配させまいと彼女が伸ばした掌についていた血を舐めたとき僕は久しぶりに味というものを感じたのだ。そして彼女に促されるまま血が溢れる傷口に顔を寄せると僕はゆっくりと彼女の血を飲み込む。口内に広がる鉄の味と匂い。美味しいとはとても思えない。でも僕は一週間ぶりに嚥下という行為を自らの意思で行えたのだ。
それから数日は僕にとっては充実した日々だった。食事が行える、空腹が満たされるということがこんなに幸せだなんて知らなかった。
僕が食事をするたびに彼女の身体は傷つくし、欠けていく場所があるけれどそれでも僕らは幸せだった。彼女は片足と指の何本かを失っても僕に笑ってくれたし、そんな彼女の身体で僕のお腹が満たされていく事が愛情だと思った。
でも幸せな日々と崩壊は紙一重。僕はあるきっかけで再び食事が取れなくなってしまった。
偶然見かけた僕の上司と隼人の情事。彼女は食事が取れずにろくな仕事が出来なくなっていた僕のために上司に身体を売っていたのだ。全部悪いのは僕。彼女を傷つけたのも恥す行為に走らせたのも汚してしまったのも僕。
でも僕以外の精液で汚れた彼女の身体を目撃した直後、僕は再びトイレに駆け込んだ。彼女を愛しているのに、信じているのに、僕のためだと分かっているのに彼女の血も肉も身体も僕にとっては毒薬のように感じた。全て体外に吐き出さないと命にかかわるような恐怖心に刈られて僕は泣きながら吐き続けた。
帰宅した僕は彼女の顔をまともに見れなかった。彼女も僕の変化に気付いて全てを悟ったのだろう。悪いのは僕なのに謝り続けた。そして自分の身体が汚れてしまったことを泣いて悔やんでいた。全部全部悪いのは僕なのに。彼女は何も悪くないのに。
僕達は泣きながら抱き合った。
僕たちの愛は傷つけあうことしか出来ない。
食事が取れなくなった僕は彼女の知人である医者から栄養剤を打たれる事になった。点滴による栄養補給。強制的だがこうでもしないと僕は死んでも何も吸収する事が出来ないだろう。身体のいたるところが欠けた彼女も医者の手で義体が贈られた。見た目だけでは過去の彼女と変わらない姿。でも僕も彼女も付き合い始めた頃に比べれば色んなものが足りなかった。
隼人は身体。僕は食欲と人間としての本能。
「もう一度やり直そうな」
点滴をしている間、そう言って手を握ってくれた彼女に僕は何度も頷いた。握り締めてきた彼女の指が足りない分、僕は強く強く彼女を握り返した。失ったものは多い。けど愛情はまだ残っていた。あの頃なんかよりも遥かに満たされた愛が。
足りなくても幸せだった。愛があれば、空っぽの部分が満たされた。
でもそれから数日後、医者から告げられた一言で僕は隼人と会う事が出来なくなった。
彼女が妊娠していること。
妊娠した時期が僕の上司に抱かれてた時期なこと。
はっきりと僕の子供という照明ができないこと。
隼人はどうしても産みたいといっていること。
僕がこんな状態であるうちは彼女に合わせられないと医者は言った。そしてその言葉どおり彼女は僕の前から姿を消したのだ。
あれから数年。僕は相変わらず食事が出来ないでいる。
今でも思い出すのは彼女の身体。そしてその血肉の味。他の誰でも駄目だ。僕が食べれるのは彼女を構成する部位だけなのだ。
そしてそんな僕の手の中には血に塗れた子供。ぐったりと動かない子供に僕は舌を這わせた。
数年ぶりにあった隼人は義足を僕に壊されて床にうずくまったまま泣いていた。許して、ごめんなさいと謝罪していた。相変わらず変わらないね。悪いのは全部僕なのに。君は何も悪くない。なのに君は謝るんだ。君の子供を突き刺した僕に。
この子供は誰の子供か分からない。隼人も医者も教えてはくれなかったから。
だから僕は隼人が姿を消した数年間、ずっと考えてたんだ。
君と僕の上司との子供なら僕は愛せない。
君と僕の子供なら僕は極上の愛を捧げられるだろう。
そして愛さえあれば、僕は疑いを持たずに食せるだろう。
ゆっくりと口に入れた子供の血。
時間をかけて僕は味わいながら飲み込む。
さぁ、僕のお腹は満たされるかな?
ぼんやりと考える僕の耳には隼人が謝り続ける声だけが聞こえた。
とうとう正ちゃんまで病みました。ちなみに上司は言うまでも無くあの方ですね。
|
|
|
|
|